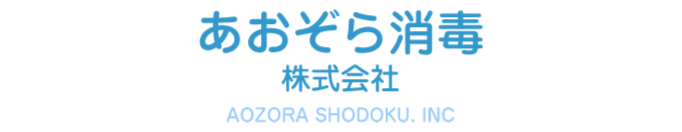シロアリ被害の基礎知識
シロアリ被害は進行が静かで、気づいたときには土台や柱の内部が空洞化していることがあります。被害の早期発見には、木材の表面だけでなく内部の変化や周辺環境まで見る視点が欠かせません。ここでは、住宅でよく見られる被害の出方と、特徴的なサインを整理します。
被害が出やすい場所
床下や玄関框、浴室・洗面所の基礎周り、勝手口や掃き出し窓の敷居は特に要注意です。これらは湿気がこもりやすく、配管の結露や雨水の吹き込みが重なると、シロアリの侵入経路になりやすいからです。屋外では束石やデッキ、庭木の切り株、薪や段ボールの長期保管場所もリスクが高まります。
見た目でわかる被害のサイン
・木材を指で押すと沈む、叩くとポコポコと軽い音がする
・床が局所的に沈む、たわむ
・壁紙の一部が膨れる、塗装が波打つ
・基礎や壁面に土でできた細いトンネル(蟻道)がある
・春~初夏の夕方に羽アリが群飛し、室内で羽だけが大量に落ちている
これらは一つでも当てはまれば要注意です。特に蟻道や羽の残骸は、現在進行形の被害を示す強い根拠になります。なお、羽アリの出現時期と色味も手掛かりです。黒褐色で小型の羽アリは雨上がりの昼〜夕方に現れることが多く、茶色系で体がやや大きい種類は梅雨〜真夏の夜間に灯りへ集まりやすい傾向があります。どちらも室内で見かけたら、屋外からの迷い込みではなく建物内部に巣がある可能性を考えましょう。
進行度の見極めと応急対応
被害のサインを見つけたら、むやみに壊さず状況を記録しましょう。蟻道や食害痕を壊すと、かえって巣の位置や活動範囲が分かりにくくなります。写真や動画で場所・大きさ・日時を残し、床下点検口や基礎周りの湿度、木部含水率の高そうな箇所を中心に観察するのがコツです。自分で触れる範囲の確認にとどめ、構造材の撤去や薬剤散布は安全面から控えてください。市販の燻煙剤は木部内部まで届きにくく、追い出して分散させるだけになりがちです。無闇な解体や過剰な水撒きも、構造と衛生の両面で逆効果になります。
自分でできる初期チェック
・床下換気口が塞がれていないか、落ち葉や物置で風が止まっていないか
・屋外に木材や段ボール、古い植木鉢を直置きしていないか
・浴室や洗面所のコーキング切れ、配管根元の湿りがないか
・基礎と外壁の取り合いに泥の線や細い土の筋がないか
・羽アリを見た日時・場所・体色(黒っぽい/茶色系)をメモしたか
専門業者へ相談する目安
次のいずれかに当てはまる場合は、早めに専門業者へ調査を依頼しましょう。蟻道が複数見える、床や柱に明確なたわみがある、浴室周りで長期的な湿気が続く、羽アリの群飛を屋内で確認した——これらは被害の進行が一定以上と考えられます。信頼性のため、調査報告書の有無、保証年数、使用薬剤と施工範囲、再発時の対応を事前に確認すると安心です。
再発を防ぐ予防とメンテナンス
駆除よりも効果的なのが、住まいを「湿らせない」「木を直置きしない」習慣です。日常での小さな工夫が、長期的な被害抑制につながります。年に一度は床下と水回りの点検を行い、梅雨前に通気と雨仕舞いを見直すだけでもリスクは大きく下がります。
日常でできる湿気対策
・床下換気経路を確保し、基礎周りに物を置かない
・エアコンのドレンや屋外水栓の排水が基礎にかからないよう誘導する
・外構の土が基礎の水切りより高くならないよう整える
・浴室の扉や窓の結露は拭き取り、換気扇を適正時間回す
リフォーム時の防蟻ポイント
・土間や玄関、浴室リフォームでは防湿シートや防蟻処理を併用する
・デッキ材は樹脂・金属・加圧注入材など耐蟻性の高い材料を選ぶ
・点検口を確保し、将来の定期点検がしやすい設計にする
・保証付きの施工を選び、施工写真と薬剤情報を保管する
以上のポイントを押さえれば、シロアリ被害の早期発見と再発防止の両立が可能です。気になる兆候を見つけたら、証拠を残しつつ冷静に確認し、必要に応じて専門家へ相談しましょう。住まいの健康は、日々の小さな習慣と計画的な点検から守られます。